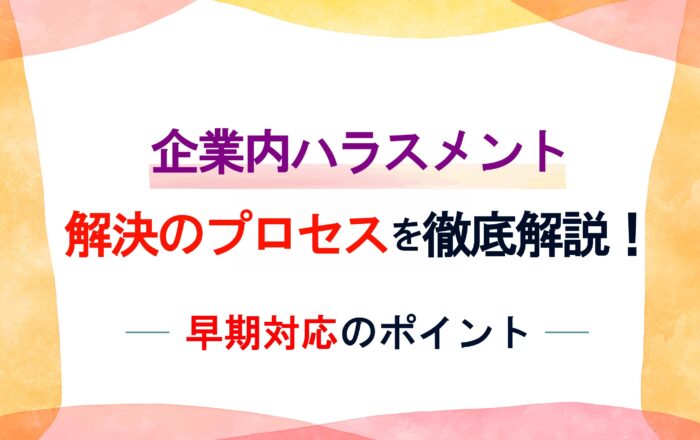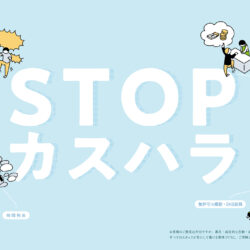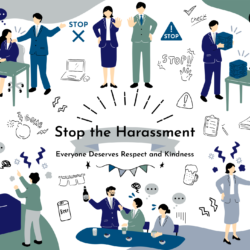はじめに
「うちの会社に限って」は通用しない時代です
ハラスメントは、どの職場でも起こり得る問題です。
決して大企業だけの話ではなく、むしろ中小企業こそ、ひとたび問題が起きたときのダメージが大きくなりがちです。
たとえば、たった一件のハラスメントがきっかけで、
・信頼していた社員が突然辞める
・社内の雰囲気が悪化する
・SNSや口コミで悪評が広まる
そんな事態に発展することも珍しくありません。
「とりあえず本人同士で話し合ってもらおう」
「今は忙しいから、あとで対応しよう」
こうした先送りが、事態をこじらせてしまう原因のひとつです。
しかし、正しいプロセスで、冷静に対応すれば解決は可能です。
大切なのは、初動の判断とその後の対応です。
本記事では、私たちがこれまで多数の企業支援を通じて培ってきた知見をもとに、
ハラスメント発生時の「基本の流れ」と「早期対応のポイント」をわかりやすく解説いたします。
“人の問題”に向き合うことは、簡単ではありません。
だからこそ、経営者や人事担当者として知っておくべきことを、ぜひ今のうちに押さえておいてください。
1.なぜ今、企業内ハラスメントへの早期対応が求められるのか
近年、企業内で発生するハラスメントに対する社会的関心が急速に高まっております。
背景には、働き方改革や多様な人材の活躍推進が進む一方で、価値観の違いや組織内の対話不足に起因する摩擦が目立つようになってきたことが挙げられます。
厚生労働省によれば、パワーハラスメントに関する相談件数は年々増加傾向にあります。また、セクシャルハラスメントやモラルハラスメントに対する従業員の意識も高まり、企業に対する説明責任や対応責任が厳しく問われるようになってきました。
万が一、ハラスメントを軽視したまま放置すれば、企業には以下のようなリスクが生じます。
・社内の信頼関係の崩壊
・離職率の上昇と人材流出
・外部への悪評拡散によるブランドイメージの低下
・労働審判や訴訟などの法的トラブルへの発展
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、「早期に適切な対応を取る」ことが何よりも重要です。
2.ハラスメントの予兆
社内ハラスメントは、ある日突然起きるように見えても、実際にはその前に小さな“予兆”が現れていることがほとんどです。この“兆し”を見逃さず、早めに手を打つことが、深刻な事態を未然に防ぐカギになります。以下はハラスメントの可能性を示す代表的な予兆になります。
■ 社内の雰囲気・言動の変化
- 特定の社員に対して強い口調・高圧的な態度を取る上司がいる → 注意喚起や指導の名目であっても、日常的な叱責や過剰な命令は、パワハラの温床となります。
- 会議や打ち合わせで、特定の社員がほとんど発言しない → 意見を出しにくい空気ができている場合、その背景にハラスメント的な圧力があるかもしれません。
- 社員同士の距離感や雑談の減少 → チーム内に気まずさや不信感が漂っている証拠です。小さなトラブルや心理的な溝が生じている可能性があります。
■ 人事データや勤怠の異変
- ある社員の遅刻・早退・欠勤が増えてきている → 精神的ストレスや職場に来ること自体への抵抗感の表れです。被害者側であるケースも加害者側であるケースもあります。
- 離職や異動希望が特定の部署に集中している → 部門内の人間関係や上司との問題が潜在化しているかもしれません。組織の“局所的な歪み”として注目すべきサインです。
- 勤怠は問題ないが、生産性や発言が目に見えて落ちている → ハラスメントを受けている社員は、心身の不調を自覚しながらも我慢して働いていることがあります。
■ 相談や報告の“ちょっとした違和感”
- 「○○さんのことで少し気になることがあるんですが…」といった曖昧な相談が寄せられる → はっきりと言葉にできないけれど、現場で何かが起きているサインです。担当者は丁寧に背景を聞き取ることが求められます。
- 業務と直接関係ない話題が雑談や社内チャットで目立つようになる → 社員の間で不満や不安がくすぶっている可能性があります。うわさ話や陰口も、職場の健全性のバロメーターです。
■ 予兆への対応の基本
予兆を感じた際には、以下のような行動が有効です。
- 信頼できる立場の社員からヒアリングしてみる
- 必要に応じて小規模な匿名アンケートを実施する
- 該当部署のマネジメント状況や職場風土を再点検する
そして、予兆を受け止める感度と、対応する勇気が何よりも重要です。
見過ごせば「発見が遅れた」では済まず、「見て見ぬふりをした」と取られるリスクもあります。
3.ハラスメント発生時の初動対応──「事実確認」の重要性
ハラスメントの申し出を受けた際、最初にすべきことは「事実の確認」です。
決して、申し出をした従業員に対して先入観をもって対応したり、安易に加害者とされる人物に指導を行ったりしてはいけません。
まず必要なのは、冷静かつ客観的に状況を把握することです。
特に以下の点に留意することが求められます。
- 「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか」「それに対してどう感じたか」など、具体的な情報の整理
- 感情的な評価ではなく、事実を時系列で整理すること
- 関係者の証言や記録(メール・チャットなど)の確認
この段階での情報収集の精度が、その後の対応の質を大きく左右します。
また、被害を訴える従業員には「丁寧に耳を傾ける姿勢」が不可欠です。
たとえ主観的な内容が多く含まれていたとしても、まずは訴えを正面から受け止めることが信頼関係の構築につながります。
4.面談の進め方と注意点──被害者・加害者・関係者からのヒアリング
事実確認を進める中で、関係者との面談が不可欠となります。
面談は「被害を訴える側」「行為者とされる側」「周囲の同僚や上司」など複数にわたるため、慎重な進行が求められます。
面談において特に重要なのは、次のような観点です。
- どの順番で面談を行うか(原則として、まずは被害を訴える側から)
- 質問内容が誘導的にならないようにする
- 面談の内容は正確に記録を残し、後日の検討に活用できるようにする
また、面談の場では「判断」や「評価」を急がず、あくまで事実の収集に徹することが基本となります。
行為者とされる従業員への面談時には、必要に応じて弁明の機会を設け、公正性を担保する姿勢も大切です。
なお、面談によって収集した情報については、関係者以外に不用意に共有しないよう厳重な配慮が必要です。
この段階での情報漏洩は、組織内の不信感を一気に高めてしまう恐れがあるからです。
5.法律的観点を踏まえた対応方針の決定
ヒアリングや面談を通じて事実が明らかになった後は、法律や就業規則に照らして適切な対応を検討します。
ここで重要なのは、「処分ありき」ではなく、「何が最善の対応か」を多角的に考えることです。
具体的には、以下のような観点をもとに対応方針を決めていきます。
1.就業規則上の懲戒事由に該当するかどうか
2.社会通念上、どの程度の行為が不適切とされるか
3.当該従業員の過去の言動や反省の度合い
4.被害を受けた側の心身の状況や今後の希望
必要に応じて、弁護士や社労士などの外部専門家と連携しながら、法的リスクの有無を確認することも有効です。
また、加害者とされる側への対応のみならず、被害者側へのフォローアップも忘れてはなりません。
メンタル面のサポート、職場復帰の支援、安全な労働環境の確保など、総合的な支援が求められます。
6.社内の信頼回復と再発防止のためにできること
ハラスメント対応は「処分して終わり」ではありません。
その後、どのようにして社内の信頼を回復し、再発防止につなげていくかが大きな課題となります。
まず、関係者の感情や立場に配慮したフォローが必要です。
必要であれば配置転換や業務調整などを行い、働きやすい環境を再構築することが求められます。
さらに、組織として再発防止に向けた取り組みを明確に打ち出すことが、信頼回復への第一歩となります。
例えば、
・ハラスメントに関する社内研修の実施
・相談窓口の明確化と、利用しやすい仕組みづくり
・上司層へのマネジメント教育の強化
こうした取り組みを継続的に行うことで、「風通しのよい職場づくり」につながっていきます。
7.外部専門家の活用で解決力を高める
中小企業では、ハラスメント対応の専門部署を設けることが難しい場合も多くあります。
そのため、専門知見をもった外部機関の支援を活用することが、実効的な解決につながります。
当社では、企業内でハラスメントが発生した際に、
被害者・加害者双方との面談、関係者ヒアリングを通じた事実確認、対応方針の助言など、一貫した支援を提供しております。
特に、第三者としての客観的な立場から対応にあたることで、企業内の対立を最小限に抑え、組織の信頼性を高めることが可能です。
企業の人的危機管理は、単なる「問題処理」ではなく、「組織の健全性を守るための経営課題」です。
ハラスメントという難しいテーマに直面したときこそ、経験と知見のある専門家の力をご活用いただければと思います。
8.まとめ
今回は、ハラスメントを早期に発見することの重要性と発生した場合の対応、そして再発防止についてご案内しました。
一方で、ハラスメントへの正しい認識が不足した弊害として「指導をしない上司」「叱責のできない上司」が増えるというハラスメントへの過剰反応も現場では起きています。
本音でぶつかり本心が言える関係作り、課題から逃げない責任感、お互いの意思表示ができる職場の雰囲気など、人と人が繋がることの豊かさを実感し心を満たし、経営者の皆さまが自信をもって責任ある言葉で組織をリードしていくことが、何よりのハラスメント防止策であることも追記します。