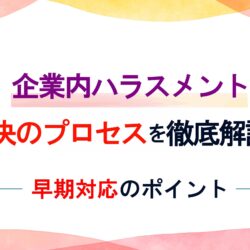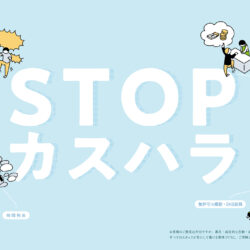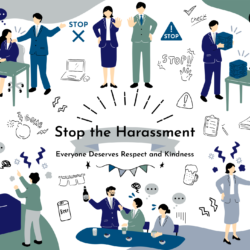職場には、法律に違反しているわけではないものの、周囲に少なからず悪影響を及ぼす社員が存在します。例えば、指示を出しても動きが遅く最低限の成果しか出さない、上司の指示には従うが主体的に動こうとしない、同僚への態度が棘のあるものになりがち──これらは一見すれば懲戒や解雇の対象にはならないため、対応を後回しにしてしまいがちです。
しかし、この“グレーゾーン”の行動を放置すると、結果的に組織全体に悪影響を及ぼし、有能な社員の離職や職場全体の士気低下につながり、企業の生産性や信頼にも大きな影響を及ぼすことになります。ただ一方で、経営者や人事担当者にとって最も扱いが難しいのがこういった社員への対応かもしれません。
本記事では、「グレーゾーン社員」の特徴や背景、放置した場合のリスク、そして企業と社員双方にとって最適な解決に導くための実務的なポイントを解説します。
法律違反ではないが職場に悪影響を及ぼす行動とは
企業の現場では、法律に明確に違反しているわけではないものの、周囲に大きな負担やストレスを与える社員の存在が問題になることがあります。例えば、業務の指示を受けても顕著に動きが遅い、周囲に皮肉を言いながら仕事をする、たばこタイムや休憩を多くとり生産性が悪い、最低限の成果は出しているが利己的な言動や行動が目立つ──こうした行動は直ちに懲戒や解雇につながるものではありません。しかし、チームワークや生産性を損なう要因となり、放置すれば企業全体の士気低下を招きかねません。
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント対策導入マニュアル」でも、「違法性の有無にかかわらず、職場の人間関係に悪影響を及ぼす行為は早期に対応することが望ましい」と示されています(厚生労働省, 2020年)。
「グレーゾーン社員」が生まれる背景と企業文化の関係
こうした社員が生まれる背景には、本人の性格や価値観だけでなく、企業文化や組織風土が影響していることも少なくありません。指示待ち型が常態化している職場では、自発的に動かなくても許される雰囲気が醸成され、結果的に「グレーゾーン社員」を助長してしまいます。
特にトップダウン型のリーダーのもとでは、上層部の指示を待つことが常態化し、社員が自ら判断したり主体的に提案したりする機会が奪われがちです。その結果、「言われたことはやるが、それ以上は動かない」という姿勢が正当化され、社員本人もそれを問題だと認識しなくなります。このような環境では、積極性を発揮する社員がかえって浮くこととなり、組織全体に停滞感が広がる危険性があります。
さらに、経営層が「成果さえ出していれば細かい言動や態度は問題にしない」という姿勢を取ると、モラル意識の高い社員の間に不公平感が募り、結果的にモラルの全体低下を引き起こします。またこうした不満の累積が離職要因になることは、様々なデータにおいても離職理由の上位に「職場の人間関係」が含まれていることからも明らかです。
放置すれば組織全体に広がるリスクとは
グレーゾーンの行動を見過ごすことにより、具体的には次のようなリスクを伴います。
◖周囲の社員が不満を募らせ、離職につながる
◖「あの人が許されているなら自分も」といった悪い前例が広がる
◖顧客対応に影響し、信用を失う可能性がある
◖問題が慢性化し、後から法的なトラブルに発展する
特に中小企業では人材の確保が難しく、ひとりの社員が会社全体に与える影響は大きくなります。、また人材定着のためには「人間関係や働きやすさの改善」は最も重要な要素の一つとされており、離職防止のためにも適切な対応をしておくことが必要です。
経営者・人事が陥りやすい誤った対応のパターン
悩ましいのは、経営者や人事担当者が「法律違反ではないから」として静観してしまう点です。あるいは逆に、感情的に叱責を繰り返し、かえって本人との関係を悪化させてしまうケースもあります。
典型的な誤りとしては、
◖本人に曖昧な注意しかしない、または放任主義
◖記録を残さず、その場しのぎで対応する
◖ちょっとした問題や周囲の不満に目をつぶってしまう
◖法的なリスクばかりを気にして本質的な改善を避ける
こうした対応の回避は、厚生労働省の「職場におけるハラスメント防止対策」指針にも反することであり、同指針においては「相談対応や記録保存の体制整備」が明確に求められています(労働施策総合推進法, 改正2020年)。
面談やヒアリングで見えてくる本音と課題
「グレーゾーン社員」の行動の裏には、しばしば本人の誤解や間違った思い込みが潜んでおり、それはコミュニケーション不足からくることと言えるでしょう。表面上の態度だけを見て良し悪しを判断するのではなく、丁寧な面談やヒアリングを通じて本人の不満や誤解の背景を探ることが重要です。
なお本人の本音を掬い取るための具体的な面談・ヒアリングの手法としては、次のようなものがあります。
- オープンクエスチョンを活用する
「どう感じていますか」「どんな点がやりにくいですか」など、Yes/Noでは答えられない問いを投げかけることで、フリートークの場をつくり、本人の考えや気持ちを引き出しやすくします。 - 相手の言葉を繰り返すリフレクション
「つまり○○ということですね」と言葉を確認しながら進めることで、双方の誤解を防ぎ、本人も安心して話すことができます。 - 事実と感情を分けて聞く
「実際に起きた出来事は何か」と「それにどう感じたのか」を分けて質問することで、その行動の真の原因がより明確につかむことが出来ます。 - 第三者ヒアリングの実施
同僚や上長に対してもヒアリングを行い、本人の言動が周囲にどう映っているかを確認します。これにより、本人の主観と周囲の認識のギャップが見えてきます。 - 記録の徹底
面談やヒアリング内容は必ず記録に残し、お互いの想いや認識の齟齬を埋めていくための重要な資料とし、ここからさらなるコミュニケーションによる相互理解を深めていきます。
こうした手法を組み合わせることで、単なる注意や叱責ではなく、本人の行動変容や組織改善につながる具体的な課題を浮き彫りにすることができます。
また本人との意思疎通に難しさを感じる場合は、外部専門家によるヒアリングを取り入れてみるのも効果的です。
本人面談だけでは見えない“真の課題”
一方で、「グレーゾーン社員」に対する面談で多くの企業が直面するのは、「本人からはなかなか本音が引き出しにくい」という壁です。1on1面談である程度の気づきはありますが、必ずしも率直な発言が得られるとは限りません。表面的なやり取りにとどまり、問題の核心が見えないまま時間だけが過ぎてしまうケースも珍しくありません。そこで必要となってくるのが、チームメンバーへのヒアリングです。
・チームメンバーへのヒアリングが有効な理由
周囲の視点から得られる声は、本人の行動を裏付ける具体的な材料となり、問題の本質を浮かび上がらせます。例えば、「業務はこなすが協調性に欠ける」「必要以上に他人に口を出す」といった行動は、本人から直接聞き出すことは難しく、同僚の証言によって明確になることが多いのです。特に「グレーゾーン社員」の影響は、周囲に不満が蓄積していることが多く、職場全体の雰囲気や士気に如実に現れます。そのため、メンバーからのヒアリングは欠かせない手法となります。
・ヒアリングを成功させるためのポイント
もっとも、聞き取りの進め方には注意が必要です。まずは、誰がどういう発言をしたかが本人に伝わらないことを明確に伝え、安心して意見を述べてもらえる環境をつくることが大前提です。加えて、単なる愚痴の収集にならないよう、「具体的にどのような問題行動だったか?」「そのとき職場内にどのような影響があったか?」といった事実に基づく情報を引き出すように問いかけることが大切です。さらに、集まった情報は告発材料としてではなく、客観的な課題の把握に活用すべきです。本人に伝える際も「誰が言ったか」とかにならないように、「複数以上のメンバーから共通して見られる傾向=客観的事実」として示すことが必要で、防御的な反応を和らげて改善に向けた対話につなげやすくすることが大切です。
・組織全体を映す鏡としてのヒアリング
また「グレーゾーン社員」の問題は、必ずしも本人の資質だけに起因するものではなく、組織文化やマネジメント体制に起因している場合もあります。そのため、チーム全体の声を拾い上げることは、問題を個人の性格や態度だけに矮小化せず、職場環境そのものを見直す契機となります。ヒアリングを通じて現場の声を可視化し、事実に基づいた解決策へとつなげることこそ、組織を健全に保つための第一歩と言えるでしょう。
トラブルを防ぐために必要な仕組みづくりと予防策
さらに、「グレーゾーン社員」を根本的に減らすには、属人的な対応ではなく仕組みとしての予防策が必要です。具体的には、
◖明確な就業規則や行動指針で、守るべきモラルについても整備し周知徹底する
◖評価制度において社員としての行動や意識についても評価に反映させる
◖定期的な面談を制度化し、問題を早期に発見するためのPDCAを回す
◖管理職に対してコミュニケーションと指導についての研修を定期的に実施する
これらは、厚生労働省「ハラスメント対策に関する企業アンケート調査」(2020年)においても効果的とされており、特に「規程の整備」「教育研修」「相談窓口の設置」が有効であるとされています。
企業と社員双方にとって最適な解決に導くアプローチ
最終的に大切なのは、企業にとっても社員にとっても納得感のある解決策を見つけることです。強制的な排除ではなく、行動改善してもらうための研修や学びの場、相互理解の場、適材適所に基づく配置転換、または本人の意志を尊重したキャリア選択など、様々なアプローチが考えられます。
なお当社では、当事者の方々との面談、および関係者からのヒアリングを通じ、法律的観点も踏まえながら、最適な形での解決をサポートしています。
「グレーゾーン社員」の対応は手順を間違えるとマイナスの結果につながることにもなりますので、適切な手順を踏んで、企業の成長と従業員の納得を両立させることで、根本的な解決につなげる必要があります。
まとめ
「グレーゾーン社員」の存在は、違法ではないがゆえに放置されがちです。しかし、その影響は間違いなく組織を蝕みます。経営者や人事担当者は、早期に問題を見極め、対話と記録を重ね、制度としての仕組みを整えることが求められています。
そして何より重要なのは、企業と社員双方にとって「最適な解決」に導こうという強い姿勢です。そのためにはかなり専門的なノウハウも必要となりますので、なかなか難しいと感じられている企業様においては、そういった事例を多く扱っている会社に相談することも必要となるでしょう。
参照元
- 厚生労働省『職場のパワーハラスメント対策導入マニュアル』(2020年)
- 厚生労働省『令和5年雇用動向調査結果の概況』
- 厚生労働省『中小企業の人材確保に関する実態調査』(2022年)
- 厚生労働省『働きやすく生産性の高い職場環境の実現に向けて』(2021年)
- 労働施策総合推進法(改正2020年, ハラスメント防止指針)