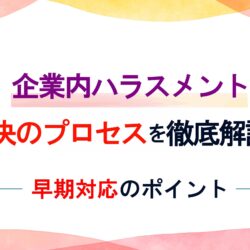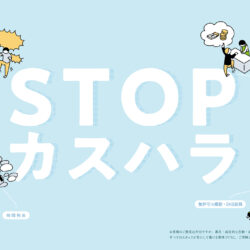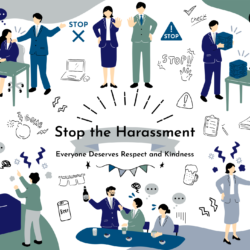はじめに──ハラスメント対策の重要性
企業内でハラスメントが発生すると、その影響は非常に深刻です。
被害者の離職やメンタル不調だけでなく、職場の生産性や信頼性にも直結します。
さらに、社外への情報流出やSNSでの拡散によって、企業の信用そのものが損なわれることもあります。
近年では、労働者が労働局や弁護士に直接相談するケースが増えており、事案によっては訴訟や労災認定に発展し、多額の損害賠償を求められる事例も報告されています。
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(2020年)」によれば、何らかのハラスメントを経験した労働者は、全体の31.5%にのぼるとされています(※出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」2020年)。
こういった現況に対して、真に危機感を感じておられる経営者は意外と多くありません。
しかし、ハラスメントは目に見えない形で進行し、顕在化したときには既に手遅れになることも多いのです。
特に中小企業では、組織がコンパクトであるがゆえに、一人のトラブルが企業全体を揺るがす事態を招きかねません。
今や企業の持続的な成長と信頼の確保には、ハラスメントに対する事前対策と早期対応が欠かせないこととなっています。
本記事では、ハラスメントの発生を防ぎ、万一の際にも冷静に対処できるよう、教育研修と職場環境の改善方法についてご紹介いたします。
事後対応にならないように、今こそ対策に取り組むべきタイミングと考えていただきたいと思っています。
1.経営層の理解と覚悟が防止対策の第一歩
ハラスメント対策は、現場任せでは機能しません。
まずは経営層が正しい理解を持ち、明確な方針を示すことがスタートラインになります。
当社が支援したある中小企業では、経営者が自ら研修に参加し、社員に対して「ハラスメントは容認しない」ことを全社員の前で宣しました。それにより社内の空気が引き締まり、また、研修により「ハラスメントに対する正しい知識」を経営層も含む社員全員で共有できたことにより「気になることを口にしていいんだ」という相談できる雰囲気ができ、大きな問題になる前の早い段階での相談が増加した事例があります。
また、今まで無意識で行っていたことも「気を付けないといけない」という認識が浸透し、特に管理職以上から部下への言葉が丁寧になったという事例もあります。トップが真剣に取り組む姿勢を示すことで、社員の意識も大きく変わります。ハラスメント対策は単なる法令遵守ではなく、自社の経営戦略の一部と言えるでしょう。
2.効果的な教育研修とは何か
様々なケーススタディを学ぶことは大変重要ですが、一方で形式的な座学だけでは、ハラスメントの防止にはなかなかつながりません。
そこで重要となるのは、実際の現場を想定した「気づき」と「体感」です。
たとえば、当社が実施する研修では、実際にあった事例研究でのグループディスカッションを取り入れています。
被害者と加害者、そして傍観者の立場から起きた問題の本質をグループで対話します。
この事例を上司としてどう解決に導くのか、それには問題の本質をとらえることが必要です。改善策を実際に遂行する順序もイメージすることで当事者意識を高めることができます。また、パワハラ・セクハラ・モラハラといった分類ごとの具体例を提示し、その違いと共に複雑に要素が絡み合う事例などから、準拠法を明確に伝えることで、曖昧な判断を防ぐことができます。
なお、研修には年齢や立場ごとの配慮も必要です。
特に管理職層には、部下との関わり方の見直しが求められることになります。
3.知識だけでなく「感情」への理解を育む
ハラスメントが生じる背景には、感情のすれ違いや認識のズレがあります。
加害者側の弁解によくあるのが、「教育・指導のつもりでやったこと」とか「コミュニケーションの一環でしたこと」といったところですが、これらは被害者側の立場に全く立てていないことの現れです。そして「そんなつもりはなかった」という言葉は被害者をさらに傷つけることにもなります。
研修では、相手の立場や気持ちに共感する姿勢を養うことが重要です。 たとえば、指導とパワハラの違いについて具体的な事例を用いて説明をしますが、パワハラに当たる言い方を『別の言い方で伝えるとしたら?』というケーススタディを繰り返し行います。また、指導のつもりで言った言葉が相手にはキツイと感じてしまうケースでは、発した本人は「悪気はなかった」「無意識だった」というのが大半であることも踏まえ、「声のトーン」や「言葉選び」にも注意することで、感情的にならず冷静に指導することが次第に理解できるようになり、部下との信頼関係が改善したという報告を受けています。
4.相談しやすい環境づくりの工夫
相談窓口があっても、使われなければ意味がありません。
人事部など社内の相談窓口は必要ですが、特に中小企業においては、相談者にとっては抵抗感がある場合もあり、上手く機能していない例もよく見受けられます。
そういう意味では、中小企業こそ第三者機関の相談窓口を設けることが有効な対策となってきます。(当社でも「KiKiCallⓇ」というハラスメントの社外窓口サービスがあります)
また、「誰に、どのように相談すればよいか」を全社員に明確に示しておくことも重要です。
社内における月1回の個別面談等ではこういったセンシティブな内容を聞き出すことはなかなか難しく、できるだけ多様な選択肢を従業員に用意しておくことが効果的です。
さらに、相談したことが不利益につながらないという安心感を与えることが、最大のポイントとなります。具体的には以下のような対応・対策が必要となります。
相談窓口の明確化と複数ルートの設置
相談窓口が一つしかない場合、相談相手が加害者に近い立場だと、相談をためらう要因になります。そのため、社内だけでなく、外部の第三者にも相談できるようにし、複数以上のルートを用意することが重要です。これにより、相談者は自分に合った安心できるルートを選ぶことができます。
匿名相談制度の導入
初期の相談段階では、匿名性が確保されることで心理的ハードルが下がります。
匿名でも相談できるチャットやメールの仕組み、外部通報窓口の活用などを整備することも効果的です。ただし、匿名相談でも対応履歴を記録し、組織として管理することが求められます。
相談者の不利益取扱い禁止を明文化
「相談したら異動させられた」「逆に職場で孤立した」「結果的に退職に追い込まれた」といった事態を防ぐためには、就業規則やハラスメント防止規程に「不利益な取扱いの禁止」を明文化する必要があります。
加えて、経営者がその方針を全社員に向けて明確に伝えておくことが不可欠です。
相談内容の秘密保持に関するルールの徹底
相談を受けた側が内容を周囲に漏らした場合、二次被害につながります。そのため、相談対応に携わる担当者には厳格な守秘義務を課し、研修によって意識を高めておく必要があります。実際の運用面でも、記録の管理方法やアクセス権限の制限などを整えることが求められます。(当社においても「コンプライアンス研修」をご提案・実施しています)
報告後の適正なフォロー体制の構築
相談後、調査・対応の進捗や対処結果が不透明なままだと、相談者は「無視された」と感じることがあります。適切なタイミングで中間報告を行い、調査の進め方や配慮事項を共有することで、信頼関係が築かれます。
この過程でも、相談者の意思や希望を十分に尊重する姿勢が重要です。
経営層の関与とメッセージの発信
「どこに相談しても同じ」と思われないためには、経営者自身が常に「ハラスメントを許さない」「相談者を守る」という姿勢を明言しておくことが大切です。そのメッセージが全社員に届くことで、職場全体に安心感が広がります。また事態が生じた際にも、経営層がとる態度、行動によって、全社員の信頼を得られるかどうかが問われることになります。
5.職場環境のチェックと改善
ハラスメントが起きやすい職場には、共通点があります。
たとえば、極端な上下関係や、長時間労働、閉鎖的な人間関係です。
こうした状況は、知らず知らずのうちにストレスを蓄積させ、その結果、感情の爆発や無意識の攻撃性につながることがあります。当社では、職場環境についてのヒアリングを実施し、社員のストレス状況や人間関係の実態を把握していきます。具体的にはキャリアコンサルタントによるONE ON ONEの実施です。誰かに話すことでたまっていた思いの発散がストレスを軽減させるだけではなく話しているうちに考えの整理できます。また、相談窓口の活用についても認識を深めるきっかけになります。
職場環境とは社員さんひとり一人の心の状態でもあるのです。
このプロセスによって、組織の潜在的な課題が明確になり、改善に向けた具体策を提案、サポートさせていただくことができます。
6.再発防止策までを見据えた対応を
問題が発生した場合、その都度の場当たり的な対応だけでは不十分です。
一度ハラスメントが起きた職場では、社員の間に不安や不信が残りますし、再発防止のためには、加害者・被害者の双方に対するフォローも必要です。
当社では、問題発生後に「再発防止プログラム」を提供しています。
内容は、行動の振り返り(起きた原因の明確化)、認知の再構築(組織としての問題点の洗い出し)、社内コミュニケーション改善(研修・面談)の三点です。
こうした取り組みによって、組織内の風通しが改善され、信頼の再構築が進んでいきます。
7.法的リスクを踏まえた対応の必要性
ハラスメントは、人権問題であると同時に、法的リスクでもあります。
たとえば、安全配慮義務を怠ったと判断されれば、使用者責任として企業側に損害賠償責任が問われる可能性があり、そのため対応には法的な知見が欠かせません。
当社では、社労士・弁護士などとも連携し、企業のリスクを最小限に抑えるためのサポートを行っています。
重要なのは、ルールや環境の整備とともに、社内において、そのルールが実効性を持つよう徹底することです。
8.組織全体で取り組む文化の醸成
最後に大切なのは、組織全体でハラスメントを防ぐ「文化」を育てることです。
一人ひとりの意識だけでは限界があります。
経営者、管理職、一般社員が、それぞれの立場ですべきことを十分に認識するために、継続的に学び続ける必要があります。まずは、社員同士が前向きに忌憚のない意見を言い合えるような職場づくりで円滑なコミュニケーションがとれる職場づくりをすることが土台となり、そこから、社員同士の関係性が改善し、ハラスメントに対する感受性も高まることになります。またハラスメント防止は、一過性の対策ではありませんので、企業文化として根づかせるために日々の実践を続けていくことが大切です。
まとめ──継続的な取り組みこそが最大の予防策
ハラスメントのない職場は、誰にとっても働きやすい職場です。
教育研修と環境改善を継続的に行うことで、未然にリスクを防ぎ、結果として、企業の成長や人材の定着にもつながります。
当社は、予防から事後対応まで一貫してサポートさせていただくことで、企業と従業員の双方にとって最適な関係性構築を目指しております。
ハラスメントの芽を早期に摘むためにも、今すぐ行動を始めてみてはいかがでしょうか?