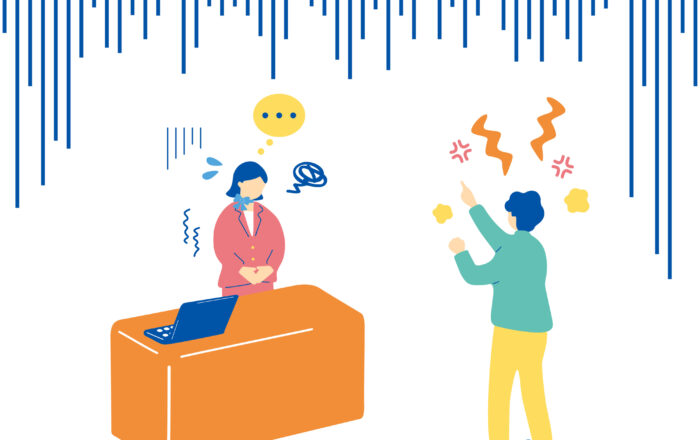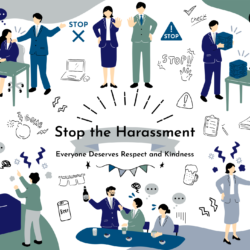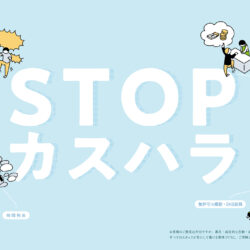はじめに──カスハラへの無関心は、自社が信頼を失う第一歩です
サービスを受ける立場の顧客が、怒声や威圧的な態度で従業員を追い詰める──こうした行為は「カスタマーハラスメント」と呼ばれ、企業にとって見過ごせない社会問題となっています。
従業員が被害を受けていても、「お客様対応だからある程度は仕方がない」と目をつぶってはいませんか?
いま企業に問われているのは「理不尽な顧客に対して、いかに自社の従業員を守れるか」です。
職場の安心感は、人材定着はもとより、今や企業イメージの根幹をも支える重要な要素となっています。
中小企業においても、相談窓口の整備や管理職の意識改革が、カスハラ対策として急ぎ整えるべきこととなってきています。
1.カスハラが企業にもたらす影響とは
カスハラが引き起こす影響は、単なる被害者の「不快感」といった感情面でのことでは収まりません。深刻なケースでは、従業員の心身の健康が損なわれ、休職や離職に至ることもあります。
企業にとってのリスクは、一時的な生産性の低下のみならず、現実的には企業の信頼性を大きく低下させるなど多岐に及びますので、そこに対しての様々な対策が必要となります。
政府は労働施策総合推進法を2025年6月4日付で改正を行い、カスハラについてもすべての企業での対策が義務化となりました(通称カスハラ対策法)。その内容は、「雇用管理上の措置義務」と言われるもので、方針の明確化、カスハラ対策マニュアルの作成と周知、研修の実施、相談窓口の設置、従業員のメンタルヘルスケア、弁護士への相談体制、記録の保管、等々さまざまな施策を講じていく必要が生じてきています。
2.企業に求められる責任と安全配慮義務
法改正により、企業には従業員に対するカスハラ防止措置義務が明確に課されることとなりました。これは、単なる努力義務ではなく、すべての企業が遵守すべき法的義務になります。
この責任は、以下の2つの柱に支えられています。
【1】「安全配慮義務」の拡張
民法および労働契約法に基づき、企業は雇用する従業員に対して、心身の健康を害することのないよう安全配慮義務を負っています。
ここには、顧客や取引先からの不当な言動(カスハラ)も明確に含まれています。
たとえば、
▪ 客からの執拗なクレームでうつ状態に
▪ 暴言の繰り返しによる退職
▪ 身体的威圧・威嚇による過呼吸や失神
といったケースは、カスハラが原因の労災認定や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【2】企業が講じるべき措置内容(厚労省指針より)
厚生労働省が公表している「職場におけるカスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、企業が取り組むべき具体的な対策としては、以下のような事が挙げられています。
① カスハラの定義や対応方針の明確化・社内周知
② 従業員のための相談体制の整備
③ カスハラに対する対応方法、手順の策定
④ 対応ルールの社内研修、教育の実施
⑤ 被害を受けた従業員へのケア体制
⑥ 再発防止策の検討・教育訓練の実施
企業がこれらを怠った結果として、万一被害が拡大すれば、「予見可能性と回避義務を怠った」として民事上の責任を問われるリスクも生じます。つまり、カスハラ対策を講じないことは、企業としての社会的信用の喪失や、組織力・採用力の低下にもつながる重大な経営リスクとなるのです。
3.被害者が声を上げにくい背景
カスハラの難しさのひとつは、「顧客からの苦情=我慢すべき」という企業文化や風土が根強く残っていることです。特にサービス業では、「お客様に対しては何を言われても我慢すべき」という誤解がはびこっており、被害者本人も「自分が我慢すれば良い」と思い込んでしまうことがあります。
またカスタマーハラスメントの被害者が「助けてほしい」と声を上げられない背景には、複数の心理的・組織的要因が複雑に絡み合っています。以下はその代表的な要因です。
① 「顧客第一」の企業文化
多くの企業では、「お客様は神様」「クレームは宝の山」など、顧客至上主義的な価値観が根付いています。これにより、たとえ顧客の言動が不当であっても、「我慢すべき」「業務の一環」と受け止められがちです。
特に新人や非正規社員、女性従業員においては、「顧客を怒らせたら自分が責任を問われるのでは」と恐れる傾向が強まります。
② 周囲の無理解や沈黙の同調圧力
被害に遭っても、周囲の同僚や上司が「気にし過ぎじゃないか」「客に対応するのは仕方がない」と受け流してしまうと、被害者は「相談しても無駄だ」と諦めてしまいます。
ときには、「報告すると面倒な従業員と思われるのではないか」というレッテル貼りへの恐怖もあります。
③ 報復や不利益への不安
相談することで、評価や人間関係に悪影響が出るのではないか、顧客から何等かの報復を受けた場合に自身の責任が問われるのではないか、といった懸念もあります。特に職場内に信頼できる相談先がない場合、被害者は「黙ってやり過ごす」ことを選びがちです。また中小企業や同族経営の会社では、こうした「組織の一体感」が逆に障壁となるケースも多くあります。
4.被害者が声を上げやすくするための対策
被害者が声を上げやすくするためには、そのための環境づくりが必要です。
その対策についてお伝えいたしましょう。
対策①:相談窓口の整備と可視化
被害者が声を上げやすくなる第一歩は、「安心して話せる場」の存在を明確にすることです。
ここでいう「相談窓口」は単に窓口を設ければ良いというのではなく、信頼性・中立性・実効性が担保された体制である必要があります。そしてとくに重要なのが、「被害を受けた従業員が安心して相談できる窓口」の整備です。
単に相談の連絡先を掲示するだけでは、実効性のある対策とはいえず、具体的には、以下のポイントを押さえる必要があります。
【1】相談者の心理的安全性を確保する運用体制
▪「報告したら不利益があるのでは」「自分が責められるのでは」といった懸念を払拭できる説明責任と守秘義務の徹底
▪匿名相談も可能なフローの導入と秘匿性の確保(社内外どちらでも)
▪初期対応で二次被害を生まないような対応マニュアルとロールプレイ研修の実施
【2】相談窓口の種類と役割の明確化
▪一次受付担当者と『専門的対応者(人事や外部専門家など)』を明確に分ける
▪外部相談窓口との連携(顧問社労士・弁護士・コンサルタント等)により、公正性と専門性を担保する
【3】相談後の流れを社内で統一する(明文化)
▪相談受付→事実確認→対応方針の決定→加害者への対応策と被害者への支援策→再発防止策
▪この一連の流れを社内ルール化し、就業規則や社員ハンドブックに反映
たとえば、「業務時間外に押しかけてきて謝罪を求める客がいた」というような深刻な事案であっても、スムーズな初動と社内共有があれば、従業員の心身の被害を最小限に抑えることが可能です。
実効性ある相談窓口の構築ポイント:
▪ 複数の相談ルートを用意する(直属上司、人事、外部窓口など)
▪ 匿名相談を可能とするシステム(メール、チャット、専用フォームなど)
▪ 相談者のプライバシーを厳守し、相談したことによる評価への影響がないことを明示する
▪ ポスターや社内掲示板、イントラネット等での周知を定期的に行い、「気軽に話せる」文化を醸成
特に近年では、『外部相談窓口(外部の専門機関との連携)』を導入する企業が増えています。外部機関であれば、利害関係がないため従業員も本音で話しやすく、問題の早期発見や対応に役立ちます。
対策②:管理職への教育
カスハラの被害を最初にキャッチするのは、現場の管理職であることが多く、彼らの対応力が企業全体の対応品質を左右することになります。ところが、管理職自身がカスハラという概念を理解しておらず、「それぐらい対応して当然」「我慢も仕事のうち」といった認識を持っていることも珍しくありません。
管理職教育で必要な内容:
▪ カスハラの定義や類型(例:暴言、土下座強要、無理な返品要求など)
▪ 早期発見のポイント(部下の表情・態度・ミスの増加など)
▪ 相談を受けた際の初期対応の仕方(共感、記録、事実確認の区別など)
▪ 企業として取るべきフローの共有(人事・法務との連携、記録の保管など)
研修は一度きりでなく、年1回以上の定期的なアップデート研修が望ましく、実例やロールプレイを交えることで理解が深まります。また、「対応できないときにどうエスカレーションするか」を知っておくことも重要です。
対策③:就業規則等での明文化
従業員の行動指針や権利保護について、「就業規則」や「社員ハンドブック」に記載することで、従業員に安心感を与えることができます。
明文化すべき内容の例:
▪ カスタマーハラスメントの定義と、企業として認めない方針表明
▪ 被害を受けた際の相談先とフローの明示
▪ 相談したことによる不利益取扱いの禁止
▪ 加害者(顧客等)への対応方針
これらの内容を文書に落とし込むことで、従業員の権利と企業の責任を明文化することになり、「相談してもいいのだ」という意識の醸成につながります。
加えて、社外(顧客・取引先)に対しても、「暴言・威圧的言動は対応対象外とする」ことを明記した文書やステッカーを掲示するなど、姿勢を明確に示すことも効果的です。
カスタマーハラスメントは、従業員の「声が届かない」「助けてもらえない」環境がある限り、決して根絶できません。
企業として、被害者が声を上げやすい仕組みと風土を整えることは、法律上の義務であると同時に、「人を大切にする組織」としての信頼を高める経営の根幹でもあります。企業文化を変えるのは一朝一夕ではありませんが、しかし、こうした具体的な施策を一つずつ実行することが、確実な変化の第一歩になるのです。
5.カスハラ対策の実践例と効果
改正法施行に先んじて、すでに先進的な取り組みを行ってきた企業の事例からは、明確な効果が確認されています。以下、業種別に代表的な2例を紹介します。
【事例①】コンビニエンスストア
◆取組内容
・2018年に「不当なクレーム対応マニュアル」を全店舗へ配布
・全国に相談窓口を整備し、加盟店オーナー・従業員が相談しやすい環境を整備
・トレーニングプログラムで「正当なクレームと不当な要求の線引き」を教育
・店舗に防犯カメラを設置し、記録を活用
◆効果
・不当な要求を可視化でき、毅然と対応しやすくなった
・従業員の退職防止につながった
・本部への相談件数が増え、支援の質が向上
・店舗スタッフの離職防止に一定の成果
【事例②】宅配運輸会社
◆取組内容
・2015年頃からすでにドライバーへの暴言・暴力を問題視し、独自の「お客様との対応ガイドライン」を整備
・現場の配達員が理不尽な要求を受けた際に、上司へのエスカレーションを明確化
・カスハラ事案を記録する専用の報告システムを導入
・悪質クレーマーについては対応の一線を設け、場合によっては取引停止を検討
◆効果
・ドライバーの心理的負担軽減
・エスカレーションのルール化により「自分一人で抱え込む」状況が大幅減少
・一定の毅然とした対応が認知され、悪質クレームの抑止効果が見られた
6.外部の専門機関と連携するメリット
中小企業にとって、社内だけで万全なカスハラ対策を構築することは容易ではありません。
そこで、外部の専門機関を活用することが有効です。
たとえば、当社では以下のような支援を行っております。
▪ 労働施策総合推進法に基づく社内体制の構築支援
▪ 社内意識調査の実施による対応策の提案
▪ 相談窓口の構築・運営支援
▪ 社内向け研修や対応マニュアルの作成
▪ 被害発生時の現場対応アドバイス
▪ 解決に向けた事実確認面談やアドバイス提供
▪ 再発防止を見据えた法的観点からの対応指針の策定
経験豊富な専門家が中立的な立場からサポートすることで、企業のリスクを最小化し、従業員の安心感を高めることができるでしょう。
7.最後に──企業文化を変える第一歩として
カスタマーハラスメントへの対応は、単なるクレーム対処法ではありません。
それは、企業が「誰を大切にするか」を明確に示す機会でもあります。
従業員の声を聴き、守る姿勢を示すことこそが、企業の信頼を高め、従業員の一体感を生み、持続可能な組織づくりへとつながるのです。
「カスハラは許されない」という価値観を、企業の中にしっかりと根付かせること。
それは経営者や人事担当者の大きな責務であり、未来への投資でもあります。
参考資料
※厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会
「職場におけるカスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)