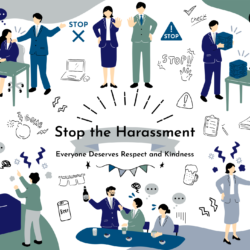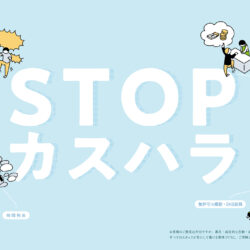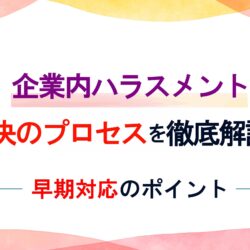「最近、誰も電話を取りたがらない」──。
中小企業の経営者や人事担当者から、そんな声を聞くことが増えています。
かつては新入社員の登竜門でもあった電話対応。しかし今や、電話が鳴るたびに社員が顔を見合わせ、誰も受話器を取らないという光景が珍しくなくなりました。
背景には、単なるマナーの問題ではなく、「電話の向こう側にいる相手がどんな反応をするか分からない」という心理的な不安があります。
また、SNSの普及により、顧客が企業へ直接メッセージを送ったり、感情的な投稿をしたりするケースも増えました。
「投稿するぞ」「拡散してやるぞ」といった言葉が、社員を萎縮させ、企業の対応を難しくしているのです。
こうした“ライトな”カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は、暴言や暴力のような極端なものではなくても、社員の心をじわじわと疲弊させ、組織全体の生産性を著しく低下させます。
本記事では、SNSや電話といった日常の業務の中に潜むカスハラの実態と、企業としてどのように備えるべきか、そして当社が支援している対策の具体的な方向性について解説いたします。
1.ライトなカスタマーハラスメントとは何か―顧客対応の“常識”を問い直す
まず、改めて「ライトなカスタマーハラスメント」とは何かを整理しておきましょう。
例えば、顧客からの電話やSNSでのメッセージにおいて、「ほかの会社と比べて対応が遅い」「今すぐ訪問しろ」「謝罪文を出せ」といったような、法的根拠の乏しい過剰な要求や威圧的な言葉遣い、明確な断りづらさを伴う言動が典型です。
実務上、こうした言動がクレームの延長線上として軽く捉えられ、対応が曖昧になることが少なくありません。
実際に、厚生労働省がまとめた「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「顧客等からの著しい迷惑行為」などに言及されており、企業が従業員を守る対応を講じることが望ましいと定められています。
また、「正当なクレーム」と「ハラスメント」の線引きについても、「要求の妥当性」や「手段・態様が社会通念上相当か」という観点で判断する必要があります。
このように、いわゆる“軽め”の接触であっても、組織としては「顧客だから何でも受け入れなければならない」という姿勢そのものがリスクとなる可能性があり、企業側としても、まず「顧客対応=尊重すべきだが、従業員を不当に追い込んではならない」という政策的な姿勢を明確にすることがスタートラインとなります。
2.SNS・電話対応における典型的な言動パターンとその兆候
電話やSNSは、顔が見えず、時間の制約もあるため、言葉遣いやトーンが重要となります。以下に典型的な言動パターンとその兆候を挙げます。
- 電話で「御社の責任として今すぐ○○しろ」「謝罪文を出せ」「◯◯を無料にしろ」と繰り返す要求。
- 「どこで番号を知ったのか? 教えろ!」など電話をかけたこと自体に対する過度な苦情。
- 電話応対で、怒声・罵声・長時間の執拗なクレームの継続。
- SNSで「この企業は○○〇〇!(悪評)」「拡散しますよ」と投稿、タグ付け、DMで言及、等々。
- 「責任者を出せ」「上司に相談しろ」など、担当者を追い詰める言動。
- 「これSNSにアップしますよ」「皆に言いふらしますよ」といった脅しの言葉。
これらは「軽め」の範囲であっても、従業員には大きなプレッシャーとなり、放置すれば心理的疲弊や離職・休職を招く要因となります。
そのため、こうした兆候を見逃すことなく、「少しでも通常の範囲を超えた言動がある」と感じたら、早期に組織的な介入を検討することが重要なアクションとなります。
3.なぜ「軽め」のハラスメントでも放置してはいけないのか―企業リスクの観点から
このような軽度のカスハラを、「まあ、うちではそこまでひどくないから大丈夫だろう」と考えるのは危険です。 “軽め”だからこそ上層部まで報告が上がらず見逃されがちになります。
結果以下のような企業リスクを抱えてしまいます。
- 従業員のメンタルヘルス低下:プレッシャーや恐怖感が慢性化すれば、休職や離職につながる可能性があります。
- 生産性低下・サービスや品質の低下:不当な対応を繰り返すことで、対応時間が増えたり、従業員が萎縮してクレーム対応の質が下がったりします。
- 企業イメージの低下・ブランドリスク:顧客がSNSで不満投稿をしたり、外部に悪評が出たりすれば、対応の甘さが見える企業として批判を受ける可能性があります。
- 法的・責任リスク:従業員の安全配慮義務を企業が怠ると、責任問題に発展するケースがあります。厚生労働省のマニュアルでも、企業が適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性がある旨が示されています。
これらを総合すると、「軽め」のハラスメントも見過ごす余地はなく、むしろ早期に「これは通常のクレームではない」と企業として判断・対応できる体制を持つことが、中小企業にとっての人的危機管理として重要です。
4.事前に整えるべきは、組織的仕組みと従業員対応の体制づくり
ライトカスハラの対応を属人的に行うと、現場ごとに対応がばらつきます。
そのため、「どこまで受け入れて、どこから拒否をするのか」という判断基準をガイドラインとして明文化し、それをスキルとして浸透させておくことが欠かせません。
発生前にしっかりと準備を進めておくことで、電話・SNS対応時の混乱を大きく軽減することができるのです。
準備すべきポイントは以下の通りです。
- 経営トップ・総務人事責任者から「カスハラを許さない」「従業員を守る」という明確なメッセージを発信する。
- 「カスタマーハラスメント対応マニュアル」で、ライトなカスハラ対応までを含めた内容を網羅し、典型的な言動例・対応フロー・記録方法・相談窓口を明記する。
- 電話・SNS対応の際の「録音・記録」ルールを定め、証拠として残せるようにしておく。
- 定期的な反復練習やロールプレイングを通じて、電話・SNSでの難しい顧客対応に慣れさせておく。
- 従業員が一人で抱え込まないよう、相談窓口・チームでの支援体制を設置する。上司・総務・法務との連携ルートを明確にする。
- モニタリング・振り返りの仕組みを設け、発生した事案を組織全体で共有し、改善策を図る。
今“電話文化”が縮小する中で、電話における人の温かさや信頼構築の機会までもが失われつつあります。
だからこそ、企業には「電話対応ができる社員を育てる」という意識が求められているのです。
電話は、単なる業務スキルではなく、顧客との信頼をつなぐ重要な接点なのです。
またSNSは、不特定多数に情報を拡散できるため、社員が対応に失敗したと感じた瞬間、「会社が炎上するのでは」という不安がよぎります。さらにSNS上での投稿は削除しても完全には消えず、企業ブランドへの影響が長く残ることもあります。
こうした背景から、「社員が過剰に謝る、反論できない、あるいは対応を避けてしまう」という現象が広がっています。
ただそれは、同時に企業が顧客との信頼関係を築く機会を失っていることを意味しているのです。
そのため、今「ライトなカスタマーハラスメント対策」を整えることは、顧客との信頼関係を再構築し、他社との差別化をはかる絶好とチャンスとも捉えることができるのです。
5.実際の対応フロー—電話・SNSで発生したときの初動と記録のポイント
実際に「電話やSNS対応で、理不尽な要求・威圧的な言動があった」と判断できた場合、次の初動対応が鍵となります。
まず、「これは通常のクレームか、カスハラか」を判断します。判断のポイントとしては、前述の「要求の妥当性」「態様が社会通念上相当か」という視点が参考になります。
その上で、以下のような対応ステップを組織的に実行します。
- 従業員が一人で対応しない/対応中に状況を複数名で共有する。
- 電話は録音、SNSはスクリーンショットを取得し、日時・担当・内容を記録。証拠保全を意識する。
- 担当者は上長・総務・法務担当に即報告し、組織で対応方針を決定。個人で判断させない。
- 顧客には毅然とした対応を示す。「調査いたします」「ご要望の法的根拠を確認します」など、言い切り・断定的な発言を避けつつ、対応範囲を明確にする。
- 必要に応じて「対応を終了させる」または「警察・弁護士を通じて対応する」可能性を示す。
- 発生後は、担当者フォロー・メンタルケア・事案の組織共有・マニュアル見直しを実施する。
6.ケース別アプローチ例 — 顧客の脅迫・誹謗中傷・過剰な要求それぞれにどう向き合うか
例えば、実務で起こりやすい典型ケースに対して、どのようなアプローチをするのでしょうか。
ケースA:脅迫的言動
電話で「このままではネットで晒す」「あとで別の者が貴社に乗り込む」といった発言。
→この場合、即座に対応記録を取り、上長・法務と連携。必要に応じて警察相談を視野に入れます。
ケースB:SNSでの誹謗中傷投稿・拡散言及
SNSで企業名・担当者名を挙げて「このサービス最悪」「晒します」と投稿。
→スクリーンショット保存、発信者情報開示を検討。企業として「個別言及には対応できかねます」と線引きを示します。
ケースC:過剰な要求・無料提供・長時間拘束
「無料にしろ」「担当者が今すぐ来い」「謝罪動画を出せ」などの要求。
→要求の法的根拠がない旨を整理し、毅然と断る体制を整え、個別対応ではなく組織で対応します。
どのケースも、「顧客=相手」というだけで“無条件に受ける”姿勢を取り続けると、企業・従業員双方にとって不利益となり得ます。こうした様々なケーススタディを社員の皆さんに共有かつ浸透させて、誰もが共通の意識でお客様に対応できるようにしておくことが重要です。
7.従業員ケアと組織風土の改善―再発防止に向けた取り組み
最後に、対応後・予防として重要な「従業員ケア」と「組織風土」の改善について述べます。
カスハラへの対応を単発事案として終わらせず、組織としての成長機会に変えることが大切です。
まず、従業員へのケアとしては、発生時の担当者がメンタル負荷を抱えないよう、上長面談・産業医や専門カウンセラーとの連携、必要なフォローアップを行うべきです。
また、組織風土としては「お客様第一」だけでなく「従業員を守る企業文化」を構築することが鍵です。例えば、顧客との対話においても「私たちは対等な立場で対応します」「無理な要求には応じません」というスタンスを明確に発信し、従業員にその判断基準を周知します。
さらに、マニュアル・対応体制・記録システム・研修などを定期的に振り返り、社内で発生した「軽めのカスハラ」事案をデータ化して傾向分析し、対応力の向上につなげます。
こうした「人的危機管理」の視点に立った取組は、結果として企業の生産性向上・従業員定着・企業ブランド強化にも寄与することになります。
まとめ
電話・SNSでのやり取りが日常化している現状において、「ライトなカスタマーハラスメント」は決して “軽く流せる” 問題ではありません。中小企業の現場では、対応力が整っていないことで被害が深刻化し、企業にとっても従業員にとっても人的危機に発展する可能性があります。
各社が蓄えておられる「人的危機に関する経験・知見・ノウハウ」を活かし、ぜひ「事前の備え」「発生時の対応」「従業員ケアと再発防止」という3軸で対策を進めていただきたいと思います。
この機会に、電話やSNSでの顧客対応に潜むリスクを整理し、的確な対策を明文化&浸透されることで、組織としての真の強さを高めることによって、他社にはない対応力と信用を生み出し、企業としての差別化戦略につながることを認識していただければと存じます。