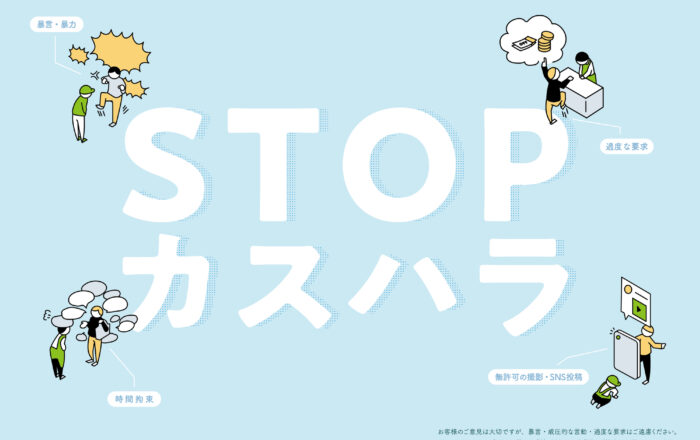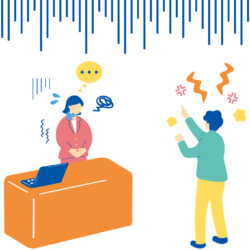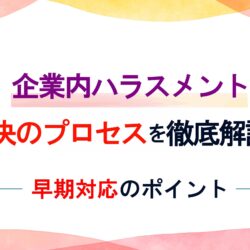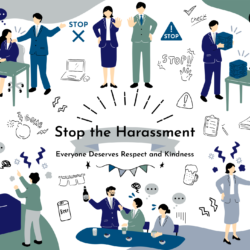ある日、受付スタッフが青ざめた表情で報告に来ました。
「お客様から、ずっと怒鳴られっぱなしで、怖くて手が震えます…」
それでも上司の口から出たのは、「まあまあ、お客様だから…」という言葉。従業員の心は、その一言で折れてしまったのです。結果その真面目で誠実なスタッフはうつ病になり退職してしまいました。
カスタマーハラスメントは、特別な業種や規模の問題ではありません。
どの企業でも起こり得る“人的危機”であり、その対応こそが会社の姿勢を象徴することになります。
あなたの会社は、従業員の「心」を守る理念と仕組みを持てていますか?
1.カスタマーハラスメントとは──「お客様の声」が暴力に変わる瞬間
カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、顧客が企業やその従業員に対して理不尽な言動や過剰な要求を繰り返し、精神的または身体的に苦痛を与える行為を指します。具体的には、次のようなケースが典型的です。
・長時間の罵倒や怒号
・無償対応の強要(「誠意を見せろ」など)
・SNSなどでの名誉毀損行為
・性的発言や身体接触
従業員は「お客様を怒らせてはならない」という意識から、反論や拒否ができず、結果的に精神的に追い詰められていきます。
このような状況が続くと、職場環境は一気に悪化し、離職率は上昇し、最終的に企業全体の信頼低下にもつながっていきます。
2.会社の対応方針が従業員の信頼につながる
カスハラの対応方針が曖昧なままでは、従業員は「自分が守られていない」と感じます。
それが積み重なると、心理的安全性が損なわれ、エンゲージメントや業務意欲が低下し、生産性はどんどん低下していくのです。
逆に、明確な対応方針がある企業では、
・対応マニュアルがあることでブレのない対応ができる
・カスハラの報告がためらわれない
・上司が毅然と対応してくれる
・組織として一貫した支援体制がある
といった「守られている感」が生まれ、従業員の安心感や忠誠心が高まります。
カスハラへの対応を通して、企業は従業員を大切にするという理念を体現できる存在だと、社員に証明することができるのです。
3.なぜ理念とカスハラ対策は直結するのか
企業理念とは、企業が「どのような価値を大切にし、どのように社会と関わるか」を示す羅針盤です。 その理念に「人を大切にする」「従業員の幸福を重視する」と明記しているならば、カスハラを放置することは理念と矛盾する行為であり、それを看過していることも理念に反する行為になります。 よく見受けられるのが、「お客様第一主義」という言葉をマネージャークラスが誤って解釈していた場合、「社員の犠牲の上に成り立つサービス」が正当化されてしまいます。
カスハラ対応は、単なるマニュアル対応ではなく、「私たちは誰を守り、どうありたいのか」という、企業の姿勢が問われる問題なのです。
4.現場での混乱を防ぐために必要な制度整備
そのため理念が定まっていても、現場で正しい判断が下せるとは限りません。
正しい判断を下してもらうためには、制度として以下のような整備が必要となります。
・【明文化】:就業規則や社内マニュアルへのカスハラ定義と対応方針の明記
・【窓口設置】:相談できる社内担当者や外部相談窓口の明示
・【教育研修】:管理職・現場スタッフへのロールプレイを交えた実践的研修
・【対応マニュアル】:対応手順、記録の取り方、通報時の対応フローの整備
これらが整うことによってはじめて、管理職や担当者は個別判断に迷うことなく、「会社としての正しい対応」が実行できる体制になります。
5.「お客様第一主義」という理念は良くない?
企業にとって「お客様第一主義」ということは経営の根本理念です。ただこの言葉は前述したように、管理職や従業員に勝手な解釈をされて、「いかなる場合でもお客様のムリを受け入れなければならない」といった誤解を招いているようなことがしばしば見受けられます。
又、「従業員の幸福」を理念に謳う会社も増えてきております。すると、カスハラが発生した時、どちらの理念が優先されるか、現場サイドで判断に困ることが発生します。
そのため、従業員が正しい判断が即座に出来るようにするためにも、様々な事例を前提として、行動するための規準づくりと制度設計が必要となるわけです。
では、カスハラ対策のために有効な制度や仕組みについてより深く見ていきましょう。
6.カスハラ対策に有効な制度と仕組み
①【カスハラの定義と対応指針の明文化】
・トップメッセージ:経営者が「社員の尊厳を守る」ことに明確な姿勢を示すことで、制度が“絵に描いた餅”にならず、実行される土壌ができる
・理念と整合する文言に統一する。企業理念・行動規範・マニュアル・社内通達すべてで、「従業員の尊重」をぶれずに打ち出すことが重要です
・就業規則や社員ハンドブックに「カスタマーハラスメントとは何か」を具体的に定義
・カスハラを受けた場合の報告義務や、対応の方針(毅然とした対応など)を明記
②【従業員保護優先の基本方針】
・「従業員の心身の安全・尊厳を守ることは、顧客満足に優先する」ことを企業理念や行動規範に盛り込む
・「お客様は神様ではない」旨を、社内教育や行動基準で明確化
③【カスハラ相談・報告窓口の設置】
・専門部署または外部窓口(例:産業カウンセラー、EAP、社労士等)を設け、匿名相談・報告ができる体制
・第三者が関与することで、公正な対応と報告者の保護が可能
④【記録化・証拠保存のガイドライン整備】
・カスハラを受けた際の音声記録、メモ、チャット履歴などの保存方法をマニュアル化
・対応フローの中に「証拠保存」「共有」「評価」のステップを組み込む
⑤【対応フロー・マニュアルの策定】
・フロントスタッフや営業社員が現場で対応する際の「対応マニュアル」を整備
例:苦情対応3ステップ(傾聴→伝達→上司へ引き継ぎ)+カスハラの見極め基準
⑥【毅然と断る判断基準の設定と共有】
・「従業員の人格を否定する発言があった場合は対応を打ち切ってよい」といった、明確な基準を提示
・この基準に基づき、上司や経営陣が「断る判断」を後押しする姿勢を周知
⑦【管理職への教育・訓練】
・「顧客対応」ではなく「部下保護と判断」に関する研修を実施
・カスハラを受けた部下に対しての初期対応(声かけ、事実確認、報告の支援)のロールプレイなどを実施
⑧【従業員の心理的安全性を守る仕組み】
・苦情対応後のメンタルケア(産業医面談や外部カウンセリング)をオプションで提供
・状況に応じて配置転換・シフト変更・一時的な業務免除など柔軟な対応ができる制度を用意
⑨【お客様への「企業姿勢」の明示】
・店頭やWebサイト、契約書などに「当社は従業員への不当な言動を容認しません」と掲示
・利用規約や顧客行動規範を定め、契約前に合意を得る形をとる(※とくにBtoB契約では有効)
⑩【再発防止の社内共有と対応記録の保管】
・カスハラ発生時には関係部署に対して「事例共有」と「対応の振り返り」を実施
・同様のケースが起きたときのための対応ナレッジとして蓄積し、業務マニュアルに反映
7.企業の取り組み事例 ~厚労省「あかるい職場応援団」の以下サイトより抜粋~
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/customers-measures/archives/1
<ヤマト運輸>
■社員の健全な業務を守るため、カスハラ対策の取組を始動
取組のきっかけの一つは、当社のコールセンター(お客様からのご相談を受け付ける部署)に、同じお客様から何度も苦情をいただいたことでした。苦情の内容は「(コールセンターの一次対応者の)態度が悪い」、「(一次対応者の)フルネームを教えろ」、「お前は向いていない。やめろ」、「まだやめていないのか」等の発言を伴うもので、繰り返される暴言によって、オペレーターが恐怖で委縮してしまいました。さらに、対応者が大変まじめな性格であったこともあり、クレームの内容を真正面から受け止めてしまったことで、「私の対応の仕方が良くなかった」、「私が会社に迷惑をかけてしまっている」と思い込み、約1か月間、コールセンター業務への復帰が困難な状況に陥りました。
このようなトラブルを踏まえ、会社として、カスハラに対する指針・考え方を整理して社員に伝える必要があるという意識が高まり、さらに経営層からも「社員の健全な業務を守らなければならない」という一言があったことから、カスハラ対策の取組が本格的に始動しました。取組は、お客様サービスセンター(従業員からお客様対応に関する相談を24時間受け付ける部署)が中心となって進めました。
取組を始めるにあたり、まずコールセンターのオペレーター向けにアンケートを実施しました。その結果、オペレーターの約8割がカスハラと思われる被害に遭っていたという実態が明らかになりました。また、アンケートの内容からは、暴言・威嚇・脅迫をはじめ、長時間の拘束や執拗な個人情報の要求といった被害が発生していたことが確認でき、これまでお客様の理不尽な発言・要求に対し、社員が我慢していたという実態も浮き彫りになり、「会社として取組を進めなければ社員を守ることはできない」、とより一層意識が醸成されました。
■実務を想定した「カスハラ発言リスト」や「文言集」を盛り込んだ対応マニュアルを作成・周知
当社では、一般社員(コールセンターのオペレーター、事務職等)向けの研修で、当社で作成した「カスタマーハラスメント対応マニュアル」の内容を解説しています。
<中略>
本マニュアルは、「カスタマーハラスメントの定義と判断基準を会社として設けて正しく対応し、お客様の著しい迷惑行為から社員を守ることを目的」とし、「(当社の)対応者への理不尽な個人攻撃には、会社として毅然とした態度で対応する」方針を掲げているもので、「カスハラ発言リスト」や「(カスハラ行為を伴うお客様への対応時に参考にできる)文言集」等から構成されています。
■対応マニュアル ~カスハラ発言リストでカスハラかどうかを判断~
「カスハラ発言リスト」には、「カスハラ発言」と「カスハラの可能性のある発言」に分けて、それぞれ発言の具体例と対応フロー(一次対応者の対応手順や管理者と電話交代するタイミング等)を示しています。当社での「カスハラ発言」は一度でも発言があればカスハラと判断する用語・フレーズ(例えば、「死ね」、「殺すぞ」等)と整理しており、このような発言があった場合、一次対応者は即座に管理者に電話を替わるフローにしています。その一方で、「カスハラの可能性のある発言」として、繰り返し発言があった場合はカスハラであると判断する用語・フレーズ(例えば、「あほ」、「お前じゃ話にならない」等)についても整理しています。このような発言を受けた場合、一次対応者は一度、その発言の対象が自身に向けられたものなのか問いかけることにしており、これによりお客様がクールダウンされた場合は通常の対応を継続し、それでも収まらない場合は管理者に電話を替わるフローにしています。
■対応マニュアル ~お客様へのお伝えの仕方に悩んだ時の文言集~
電話対応中にお客様への伝え方に悩んだとき、参考にできる情報として、「文言集」を掲載しています。例えば、管理者に電話を替わる際のフレーズとして、「恐れ入りますが、上席にお電話を代わらせていただきます。」といった対応例なども掲載しています。
<中略>
■専用相談窓口を活用したお客様対応に関するOJT
マニュアルには専用の相談窓口の連絡先を掲載しています。同連絡先は社内イントラ等で周知しており、いつでも社員の目に入るような形にしています。社員からお客様サービスセンター(専用の相談窓口)にカスハラに関する相談の電話が入った際は、直接の対応や、ただ指示を出すだけでなく、「この場合はこう考えてみては?」といったレクチャーをOJT的に行うこともあり、相談者のカスハラに関する判断力の向上に繋がっているとも考えています。同時に、カスハラ判断について、誤った認識や判断とならないようアドバイスもしています。
■どのコールセンターでも対応できるようにカスハラ情報は全社で共有
カスハラ行為を伴うお客様の対応を実施した際は、必ずレポートを作成し、社内データベースに登録するようにしています。レポートには、問題があったお客様の情報(連絡先や発言内容等の詳細)を記録し、必要に応じて、今後連絡があった際の対応方法についてお客様サービスセンターから案内しておくこともあります。当社のコールセンターは全国各地に点在しておりますが、データベースの内容は全社で共有して確認することができるため、お客様からの連絡に対して、どのコールセンターでも適切に対応できる仕組みとなっています。
<中略>
■社内にカスハラという概念が浸透しつつあることが取組の成果
カスハラという用語・概念が社内に浸透していることが本取組の一つの成果だと捉えています。これまでは社員がクレームの内容を正面から受け止めてしまい、たとえ社員に非がなくても必要以上に自分を責め、悩みを抱え込んでしまう者もいました。しかし、現在は経営層をはじめ、社内全体の意識が少しずつ変わりつつあり、カスハラ行為をされるお客様に対しては徐々に毅然とした対応ができるようになったという実感があります。
8.企業として「誰を守るのか」を明言する
お客様との信頼関係は大切です。
しかしそれと同じくらい、いや時にそれ以上に、「社員の尊厳と安全」を守ることが、持続可能な経営には不可欠です。「顧客満足」と「従業員満足」は、決して相反するものではありません。
むしろ、従業員が安心して働ける環境があるからこそ、お客様にも質の高いサービスが提供できるのです。
最後に、企業として次の問いに答えてみてください。
「あなたの会社の理念は、従業員を守る指針になっていますか?」
この問いに「はい」と胸を張って答えられるよう、カスタマーハラスメントへの向き合い方を、改めて見直す時期にきています。
まとめ
・カスハラは企業全体の危機につながる
・企業理念と対応方針は密接に関係している~まず「誰を守るのか」~
・明文化、研修、相談体制など制度整備が必要
・実例から学ぶことで、自社の対応のあり方が見えてくる
・最も大切なのは理念を正しく理解してもらうという経営者の姿勢