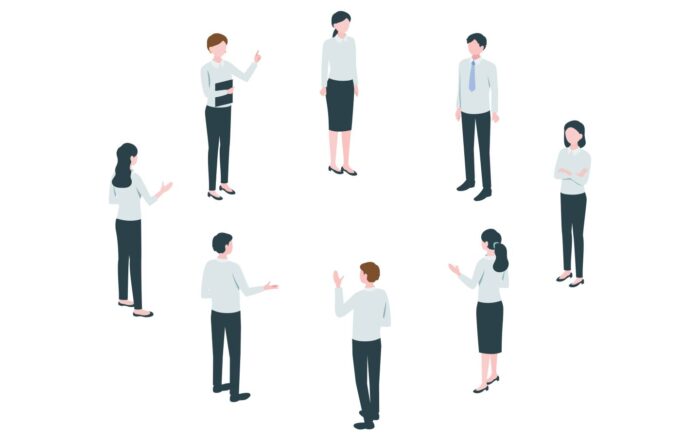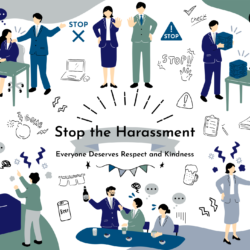前回のメルマガでは、「ハラスメントには予兆がある」という話をお伝えしました。
今回は、実際に“サイン”をキャッチしたあと、経営者としてどう動くかについてお伝えします。
対応の3ステップ
① 事実の中にある、“背景”をよく聴く、よく視る
いきなり「誰が何を言ったのか教えて!」「なんでそんなことになったの?」と詰問するのは逆効果です。最初は身構えることもあります。人事担当者(経営者)に「何を言っても味方してくれないかもしれない…」と感じた瞬間に、心を閉ざします。
被害を訴える相談者は、聞き手が自分の味方なのかどうか、迷いと不安をもっていることを理解し、その気持ちを尊重しているという姿勢で、しっかりと相手を視る、しっかりと聴く、そして不安を受け止めることが大切です。否定されずに聴いてもらっているという安心感が信頼の第一歩です。
ただし、話の中で感情の揺れを感じても、その感情に寄り添い過ぎず冷静に「どんなふうに感じた?」「困ったことはなかった?」という視点で、誰が良い悪いではなく、「なぜこうなったか」についてを俯瞰して把握することで、起きている現象だけではなく、職場全体の課題が見えてきます。
② 会社として対応する意思を示す
次に、解決に向けて相談者と会社側が共通の認識をもって、協力体制と信頼関係を築くことが大切です。
ハラスメントの訴えが妥当か否か、どちらが良いのか悪いのかという結論を急ぐ前に、会社としてその訴えを「重要なこと」として扱うという姿勢を示すことです。それが相談者にとって「話してよかった」と思えるかどうかの分岐点になります。
「話してくれてありがとう。会社としてしっかり受け止める、善処する。」というひと言が、解決に向けての信頼関係構築の第一歩です。
・解決への施策・スケジュールを示すこと
・相談者のプライバシーと情報の機密事項を守ること
・窓口を決めること
なども伝えることが信頼関係構築の重要な意思表示です。
③ 再発防止策までを見据えた対応を
急を要することと長期的な改善策を分類し、優先順位を付けることも大切です。
必要に応じて配置換えも行う場合もありますが、一時的な「注意」や根本解決にならない「配置換え」だけでは不十分です。
起きた原因と課題を冷静に分析し、同じことが起きないように、仕組みやルールを見直すこと、また、管理職に対して、指導スキルやハラスメント研修を導入するなど、再発防止策に踏み込むことが経営者の責任です。
※次回、“起こさない組織”作り、経営者がリードする「土台づくり」についてご紹介します。
最後に、「ハラスメントは防げます」
たった1人の声であっても、組織全体に与える影響は大きいということに気づき、トラブルが大きくなる前に社員の声を拾い、経営者が正しい対応をする力がある組織であれば、ハラスメントは防げます。