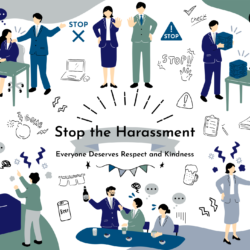① “指導とハラスメント”の境界線を曖昧にしない
叱る・指導すること自体は必要です。ただし、今の時代に合った伝え方、受け取り方への配慮が求められます。
多くのトラブルは、
「厳しく言ったつもりはない」「愛情のつもりだった」「悪気はなかった」
が通用しないことで起きています。指導者側の思いだけでなく、受け手がどう感じたかを尊重する視点を、組織全体に根づかせる必要があります。
そのためには、定期的な研修・対話の場が不可欠です。
➁ 教育体制は“ルール”ではなく“空気づくり“がカギ
就業規則やハラスメント方針は、どの企業にも整備されています。しかし、問題が起きるのは「空気」が追いついていない職場です。
たとえば、「言いづらい」「相談できない」「結局何も変わらない」という雰囲気が蔓延していれば、制度は機能しません。
心理的安全性を高めること
そのためには、
小さな意見も拾い上げる経営の姿勢
その姿勢が見える場づくりが有効です。
・月1回の1on1面談(第三者を介して実施するケースも)
・小集団での対話会、クロストーク
・ハラスメント事例をもとにしたケーススタディ研修
これらはすべて「社員の声が届く」空気をつくるための土台です。
③ “対応した”ではなく、“変わった”を実感できる組織へ
社員は、経営者の言葉よりも、行動と変化を見ています。
「対応した」ではなく、
「あの件をきっかけに、会社が変わろうとしている」
と感じてもらえるかどうかが、信頼回復のカギです。
だからこそ経営者が、
・部下任せにせず、自ら対話に出ていく
・学びの場に共に参加する
・ミドル層への継続的な教育に投資する
そういった「本気の姿勢」を見せることが、結果的に離職やトラブルの予防にもつながります。
どんなに制度を整えても、空気は放っておけば古いままです。
経営者が旗を振り「この会社は変わる」というメッセージを、日常の中で伝え続けること、それが“起こさない組織づくり”の第一歩です。
そして、正しい対応をする力とは = ハラスメントが起きにくい組織”そのものをつくること、その鍵を握るのは、やはり経営者の姿勢と意思です。